- 人材定着
- 育児休業
- 介護休業
介護事業所の、育児・介護休業法活用で実現する
「働きがい」と「人材定着」
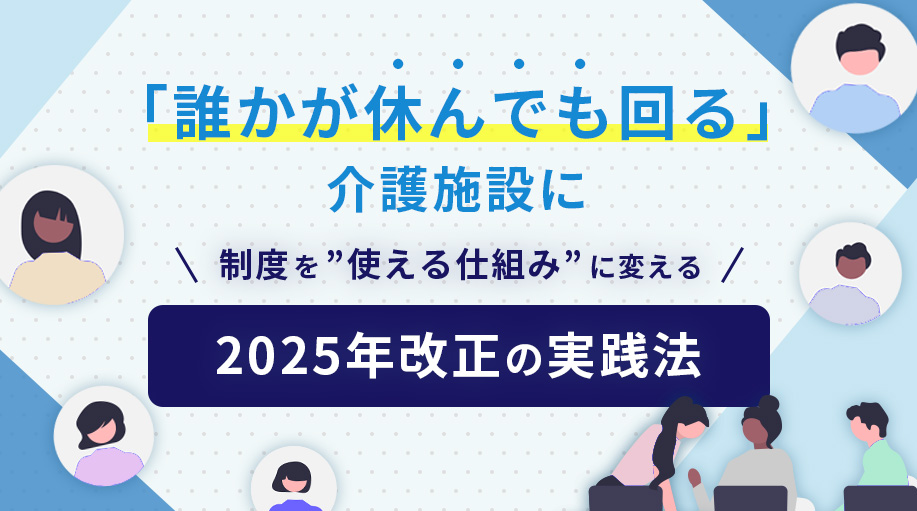
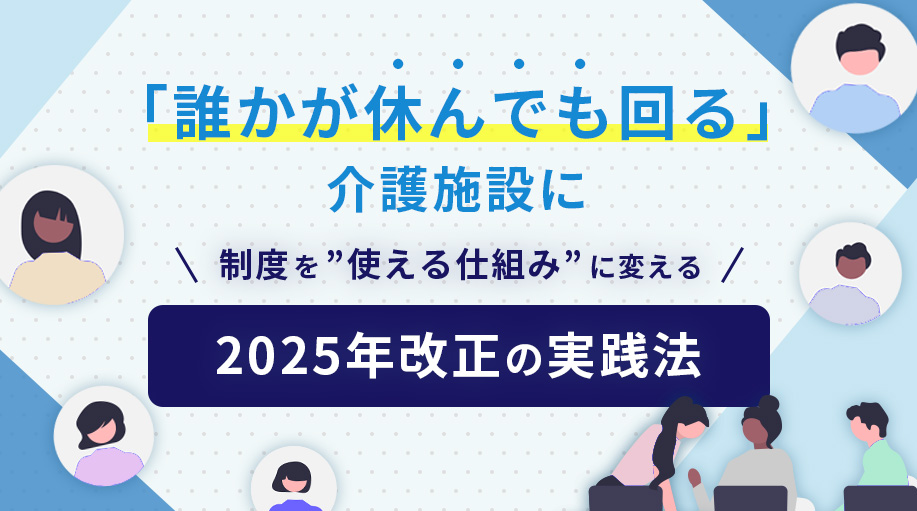
![]() はじめに
はじめに
日本社会の高齢化の波は、介護サービス業界に大きな変化を求めています。介護の必要性が増える一方で、働き手不足が大きな課題です。このような時代に、従業員が安心して働き続けられる環境を整え、様々な人材を確保することは、もはや単なる福利厚生ではなく、会社の戦略としてとても大切な状況になってきています。それは、福祉サービスを提供している介護事業所においても同じことがいえます。
本記事では、育児・介護休業法の説明から、介護事業所が取り組むべき具体的な対応、そして職員が辞めるのを防ぎ、長く働いてもらうための考え方を変えるポイントまで、幅広くご紹介します。
INDEX目次
第一章育児・休業法とは?―背景と2025年改正のポイント
法律の目的と社会的背景
育児・介護休業法は、働く人が仕事と子育て・介護を両立できるよう支援するために設けられた法律です。働きながら子育てや介護をできる環境を整えることによって、「少子化」や「介護離職」などの社会課題に対し、持続可能な社会の実現を目指しています。
実際、毎年約10万人が介護を理由に離職しており、これは労働力の減少や、年金・医療などの社会保障制度に深刻な影響を及ぼす可能性があります。こうした現状に対して、政府は「異次元の少子化対策」として、男性の育児休業取得の促進をはじめとする多角的な支援を進めています。
この法律は、単に個人のワークライフバランスを支えるものではなく、社会全体の安定や経済の活性化を支える基盤のひとつでもあります。
法律改正の意義と方向性
育児・介護休業法は、社会環境や労働市場の変化に応じて定期的に見直されていきました。2025年4月1日には、これまでの「休暇制度」に加え、「柔軟な働き方の選択肢」を広げる大規模な法規制が行われました。
従来は「制度があっても使いづらい」とされることが多く、特に中小企業や介護業界では実際の運用が進まない課題も多くありました。今回の改正では、企業側に対し「使える制度の整備」と「従業員との個別対応」を求める方向性がより明確になっています。
2025年4月改正の主なポイント
以下は、2025年4月の改正で特に注目される6つのポイントです。
読み手が該当する内容をすぐ把握できるよう、項目別に整理しています。
1.子の看護休暇の対象拡大と制度見直し
・名称変更:「子の看護休暇」→「子の看護等休暇」
・対象年齢の拡大:「小学校入学前」→「小学校3年生の修了時まで」
・対象理由の追加:「学級閉鎖」「入園式・卒園式」なども休暇理由に含まれる
・入社6か月未満の従業員も対象に(従来は除外)
2.残業免除の対象拡大
・対象拡大:「3歳未満」→「小学校入学前の子を育てる従業員」
・従業員の申請があれば原則残業免除
3.育児のための柔軟な働き方支援(努力義務化)
・3歳未満の子を育てる従業員への時短勤務が困難な場合、テレワークなど代替措置を企業に努力義務として課す
・フレックスタイム、時差出勤、育児支援休暇(年10日以上)などを用意し、従業員が選択できる体制を推奨
4.介護離職を防ぐ支援の強化
・介護が必要となった従業員への制度周知と意向確認が企業の義務に
・介護保険制度の周知も推奨され、介護との両立に向けた柔軟な勤務形態(時短、フレックス、テレワークなど)の導入が求められる
・「休暇取得を控えさせるような言動は支援とは認めない」と明確化
5.育児休業取得状況の公表義務の対象企業拡大
・適用範囲:「従業員1,000人超」→「300人超」企業まで拡大
・数値目標の設定・公表も義務に(次世代育成支援対策推進法の延長=2035年まで)
6.育児時短就業給付の創設
・対策:2歳未満の子を育てる時短勤務の従業員
・内容:減収分の約10%補填する給付制度(新設)
まとめ:法改正のポイントを“自分ごと”として捉えるために
今回の改正では、特に以下の2点がこれまでと大きく異なります。
・「使える制度」にするための企業側の努力義務と義務化の明確化
・「個別の職員」に応じた対応が求められる点(画一的ではない)
読み手によって注目すべきポイントは異なりますが、本記事では「介護施設の経営者・管理者」「職員(従業員)」それぞれの立場から視点で、次章以降にわたって具体的に解説していきます。
第二章育児・介護休業制度の基本と介護施設としての対応
この章では、育児・介護休業制度の基本的な内容と、それに対して介護施設がどのように対応すべきかを、職員向けの視点と施設側の対応視点に分けて整理します。
【職員向け】育児・介護休業制度の基本
育児休業制度
育児休業の対象は、妊娠・出産を申し出た従業員や、3歳未満の子を育てる従業員です。
対象となるには、以下の条件を満たす必要があります。
・育休開始前の2年間に、一定の勤務実績があること
・雇用保険に加入していること
※派遣社員やパート社員でも、条件を満たせば対象になります。
休業期間と制度の特徴
・原則:子が1歳になるまで(最大2歳まで延長可能)
・分割取得:最大2回に分けて取得可能
・パパ・ママ育休プラス:夫婦で取得する場合、子が1歳2ヵ月まで延長可能
・産後パパ育休(出生時育児休業):出生後8週間以内に最大28日、2回まで取得可能
給付金と社会保険料
・育児休業給付金
・休業開始~180日:賃金の67%
・181日目以降:賃金の50%
・育児休業中は、健康保険料・厚生年金保険料の支払いが免除されます。
介護休業制度
介護休業は、次のような条件を満たす家族を介護する従業員が対象です。
・病気や障害で2週間以上継続的な介護が必要
・対象家族:配偶者、親、子、祖父母、兄弟姉妹、孫など
※日雇い労働者は対象外
制度の概要
・介護休業
対象家族1人につき最大93日まで取得可能(3回まで分割取得可)
取得申請は原則、休業開始の2週間前までに書面で提出
・介護休暇
年5日(対象家族が2人以上なら10日)
1日単位または時間単位で取得可能
給付金
・介護休業給付金
給料が支払われない場合、賃金の67%が支給されます
支給は後払いのため、生活資金の準備が必要です
【施設向け】制度を「使える」状態にするための対応
育児・介護休業制度は「制度がある」だけでは不十分であり、実際に使いやすい環境を整えることが施設に求められます。特に2025年4月の改正では、「制度の個別周知と意向確認」が義務化されたため、より積極的な対応が必要です。
制度を職員に伝える・相談しやすくする
・制度内容の明示(パンフレット・イントラネットなど)
・誰に相談・申請すればよいかを明確に
・管理職への研修で制度活用を後押しする意識づけ
育休・介護休業からの職場復帰を支援する
・復帰前の面談を実施し、不安や希望を把握
・業務量や内容の調整
・キャリア形成の機会が継続するようサポート
法改正に伴う義務の実施(2025年~)
・介護が必要になった従業員には、制度の個別説明+意向確認が必須
・画一的な対応ではなく、職員ごとの事情に応じたサポートが必要
まとめ
介護施設においては、育児・介護休業制度を正しく理解し、職員が安心して利用できる環境を整えることが、離職防止や定着率の向上につながります。特に改正後は、「申出があった職員に対する個別説明と意向確認」が法的義務となったため、形式的な対応ではなく、実質的に支える姿勢がますます重要になります。
第三章小規模介護事業所でもできる!制度活用の工夫と対応策
育児や介護との両立支援は、規模の大きな法人だけが取り組むものではありません。小規模な介護事業所でも、工夫次第で制度の活用を促し、職員のやる気や定着率を高めることが可能です。
この章では、小規模事業所ならではの課題と、それに対する現実的な工夫や対応策をご紹介します。
小規模事業所が抱える共通の悩みとは?
小規模な介護事業所では、次のような状況が制度活用の妨げになることがあります。
・少人数体制で「一人欠けると回らない」業務構造
・担当業務の属人化が進み、引き継ぎが難しい
・法改正や制度の詳細を把握・対応する余裕がない
・書面化されたルールや運用マニュアルが未整備
しかし、こうした制約があるからこそ、業務の仕組みを見直すことが離職防止と事業継続につながる鍵になります。
小規模事業所でも取り組める5つの工夫
1.業務の「見える化」と属人化の回避
・業務手順や対応フローをマニュアル・チェックリスト化
・複数人で同じ業務を担当できるようローテーションを組む
これにより、「○○さんが休んだらできない」という状況をなくし、休暇取得に対する心理的な負担も軽減できます。
2.柔軟な勤務形態の導入
・勤務時間の繰上げ・繰下げ(時差出勤)
・一部の時間帯のみの短時間勤務
・シフト調整で業務量を均等に配分
小回りの利く体制だからこそ、職員の状況に合わせた対応がしやすいのは小規模事業所の強みでもあります。
3.丁寧なコミュニケーションと信頼構築
・定期的な面談や1on1ミーティングの実施
・上司や管理者からの「休んでも大丈夫」のメッセージ発信
こうした日々の関わりが、制度利用への心理的ハードルを下げ、職員の安心感と信頼を高めます。
4.両立支援等助成金の活用
・厚生労働省が実施する「両立支援等助成金」などを活用
→ 育児・介護両立に取り組む法人に支給される制度
→職場環境の整備費用(マニュアル整備や短時間勤務制度の導入など)をカバー
助成金は制度を実施しやすくする後押しになります。ハードルが高いと感じる内容も、経済的負担が減ることで実行しやすくなります。
5.社会保険労務士などの専門家に相談する
・制度の導入や就業規則の見直し
・実務対応に関する疑問や不安の解消
外部の専門家と連携することで、「判断に迷ったまま放置する」ことがなくなり、リスクを未然に防ぐことができます。
まとめ
小規模事業所だからこそ、「制度が使えない」ではなく、使いやすくするための工夫がより効果的に活きる場面が多くあります。
制度を整えることは、一時的には手間かもしれませんが、それによって「職員が安心して働き続けられる職場」が実現すれば、結果として安定した運営と人材確保につながります。
次章では、こうした制度を“形”だけでなく、文化として定着させるための意識改革のポイントについて解説します。
第四章制度を“活かす”ための意識改革―定着・離職防止につながる考え方
育児・介護休業制度を「整備すること」だけでは、職員の定着や離職防止にはつながりません。
制度を実際に使ってもらうための“文化づくり”や、日頃の意識づけこそが、介護施設における人材戦略のカギです。
この章では、制度を職員が安心して利用できるようにするための3つの視点から、意識転換のポイントを解説します。
法令遵守は「職員への配慮」であると伝える
「知らなかった」を防ぐ情報提供の重要性
2025年の法改正では、介護が必要になった従業員への制度の個別周知と意向確認が義務化されました。
これは単なる事務対応ではなく、従業員に対して「困ったら相談してほしい」「一人で抱え込まなくていい」という法人側のメッセージにもなります。
特に介護に関する悩みは、同僚にも言いにくいケースが多く、本人が孤立してしまうリスクがあります。
会社側から積極的に声をかけ、支援制度の存在や介護保険制度もあわせて案内することで、「自分は大切にされている」と感じてもらうことができます。
ハラスメント防止は「安心の保証」
育児・介護休業に関する嫌がらせ(マタハラ・パタハラ・ケアハラ)は、制度があっても使われない大きな要因です。
企業には防止措置の実施が求められていますが、これは単なる義務ではなく、**「安心して働ける職場をつくる約束」**でもあります。
・研修の実施
・専用の相談窓口の設置
・ハラスメントに該当する事例の明示 など
グレーゾーンをなくす取り組みを進めることで、制度を安心して使える職場文化の土台が築かれます。
柔軟な働き方は「個人に寄り添う選択肢」として提供する
選択肢があることで信頼につながる
2025年の法改正では、育児支援として複数の働き方(時短勤務・時差出勤・テレワークなど)を提示し、職員が選べる仕組みを用意することが法人に求められています。
これは単なる制度の整備ではなく、**「職員が自分に合った働き方を選べるようにする姿勢」**の表れです。
職員が「自分の事情に合わせて柔軟に働ける」と実感できることは、法人への信頼感に直結します。
キャリアに不安を抱かせない配慮も必要
制度を利用することで、「昇進に影響するのでは?」「責任ある仕事を任されなくなるのでは?」といった不安を感じる職員もいます。
特に育児中の女性が昇進しにくくなる「マミートラック」問題は、長期的な人材確保を阻むリスクになります。
・復帰前の面談での丁寧なヒアリング
・復帰後の業務内容や評価制度の見直し
・中長期のキャリアパスの提示
といった配慮により、「制度を使っても不利にならない職場」であることを明示していくことが重要です。
「チームで助け合う」文化を仕組みとして整える
「休んでも回る」体制づくりが心理的ハードルを下げる
制度を使いたくても、「周囲に迷惑がかかるのでは」と気を遣って申請をためらう職員は少なくありません。
この“遠慮”をなくすには、個人の気持ちだけではなく、業務の仕組みを変えることが必要です。
・業務マニュアルやタスク管理ツールの活用
・担当業務の分散・ローテーション
・「誰が休んでも回る」体制づくりの明文化
これにより、「あなたの育児・介護は、チームみんなで支える」という文化が形成され、職員の心理的な負担を大きく軽減できます。
まとめ
育児・介護休業法への対応は、単なる「法令対応」ではなく、職員との信頼関係を築くための経営施策のひとつと位置づけることが大切です。
・法令遵守を「従業員への配慮」として伝える
・嫌がらせを許さない姿勢を明確にする
・柔軟な働き方を「選べる選択肢」として用意する
・「誰が休んでも大丈夫」な業務設計を進める
これらはすべて、「この法人なら安心して働き続けられる」と感じてもらうための仕掛けです。
制度を“活かす”ことは、現場の人材を“活かす”ことにつながります。
第五章介護業界での両立支援やテレワークの具体例
介護事業所では、業務の多くが「対人援助」であるため、テレワークには不向きという印象を持たれがちです。しかし、実際には、業務の一部は在宅でも対応可能であり、両立支援の選択肢として活用が進んでいます。
この章では、介護施設におけるテレワークの具体的な業務例、メリット、導入時の注意点を【施設向け】【職員向け】の視点で分けて紹介します。
介護施設でテレワークが可能な業務とは?
介護施設の業務は大きく分けて次の2つに分類されます。
・直接支援業務(例:入浴・排泄・食事介助など)
・バックオフィス業務(例:事務・管理・情報共有・教育など)
テレワークが可能なのは、主に後者のバックオフィス業務です。
国も「直接支援に支障が出ない範囲であれば、テレワークは可能」と明言しており、柔軟な運用が推奨されています。
1.事務・管理業務
・勤怠・給与・介護報酬の管理(各種システムを活用)
・書類作成(記録の一部、報告書、マニュアルなど)
・採用・労務手続き(書類選考、面接日調整、資料作成など)
2.情報共有・研修・相談業務
・スタッフ間の情報共有(ビジネスチャット、記録ソフトなど)
・会議のオンライン化(施設内会議、委員会など)
・eラーニング・動画研修(基礎研修、感染症対策など)
テレワーク導入のメリット
【施設にとってのメリット】
・人材定着・離職防止につながる
育児・介護との両立がしやすくなることで、退職防止に直結
・業務効率化・生産性向上
ペーパーレス化や業務分担の見直しが進む
・多様な働き方の受け入れによる人材確保
子育て中・介護中の人材も戦力として活用しやすくなる
【職員にとってのメリット】
・通勤負担の軽減/体力的・精神的余裕が生まれる
・ワークライフバランスの改善
・育児・介護との両立に柔軟に対応できる
テレワークという選択肢があることで、「この職場なら働き続けられる」と感じる職員が増えることが期待できます。
導入時に配慮すべき6つのポイント
制度として導入する際には、次のような実務上の配慮が必要です。
| 1 | 業務の切り分けと明確化 | どの業務がテレワーク対象かを明文化し、対象職種・範囲を明確にする |
| 2 | 勤怠管理と評価制度の整備 | 勤務実態を正確に把握できる仕組み(勤怠システム等)と、在宅勤務者も公平に評価できる制度設計 |
| 3 | 情報共有体制の強化 | チャットツールやオンライン会議を定着させ、現場との連携を維持 |
| 4 | 情報セキュリティ対策 | VPN接続、暗号化、クラウドストレージの適正利用と、個人情報の取り扱いルールの周知徹底 |
| 5 | 公平性への配慮 | テレワークの可否について「なぜこの職種は対象なのか」を丁寧に説明し、現場職員との不公平感を抑える |
| 6 | 運用ルールの文書化と共有 | 認識のずれを防ぐため、制度内容・対象・運用フローは書面で明記し、全職員と共有することが重要 |
まとめ
介護施設におけるテレワークは、すべての職種に適用できるわけではありませんが、業務の一部を切り出して活用することで、制度利用の幅が大きく広がります。
これは単に「働き方の選択肢を増やす」ということにとどまらず、職員の定着や業務の効率化につながる「組織づくり」の一手にもなります。
次章では、制度が形だけに終わらず、本当に“使える”仕組みとして根付かせるために必要な視点を、全体のまとめとしてお伝えします。
まとめ
―制度を“使える”環境に変えることで人が育つ
育児・介護休業法は、少子高齢化が進む日本社会において、働く人々がライフステージの変化と向き合いながらも、安心して働き続けられる社会の実現を目指した制度です。
特に2025年の法改正では、育児・介護を支えるための制度がさらに拡充されると同時に、企業・施設側には「制度の個別周知」「柔軟な働き方の提供」といった、より積極的な取り組みが求められるようになりました。
制度があっても“使われない”現実
・男性の育児休業取得率は2022年度で17.3%
・介護休業取得率は男女ともに1.4%
このように、制度が整っていても、実際には利用が進んでいないのが現状です。
その背景には、次のような課題があります:
・「制度を使うと迷惑をかけるかも」という職員側の心理的ハードル
・代替要員の不在や、業務の属人化といった現場の構造的な問題
・制度利用によってキャリアが停滞することへの不安
制度・運用・意識の“三位一体”での改革が必要
こうした悪循環を断ち切るには、以下の3つの視点での取り組みが欠かせません。
1.制度を整える(法令・制度設計) ・法改正に合わせたルール整備、助成金の活用
2.運用を仕組みにする(誰でも使える状態にする) ・業務の見える化・属人化の回避、復職支援の仕組み化
3.意識を変える(制度は“支え合い”の道具であると伝える) ・チーム文化の醸成、ハラスメント対策、柔軟な対応を“信頼”として示す姿勢
誰もが安心して働き続けられる職場づくりへ
介護の現場を支える職員一人ひとりが、育児や介護というライフイベントを迎えても、自分のキャリアを諦めることなく働き続けられる。
そんな職場環境をつくることが、これからの介護事業所にとっての競争力であり、人材定着の最大の鍵になります。
制度を“使えるもの”として浸透させ、育児・介護を“支え合える職場文化”として根付かせる
この取り組みが、これからの介護業界の標準になっていくことが求められています。
引用文献